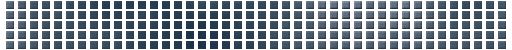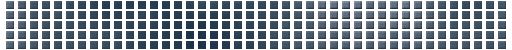
今日、声の音楽においては、極めて多彩な音色を聴くことができる。特に、世界中の民族音楽からの影響は大きく、様々な発声を生かした作品が数多く見られる。
私の声の演奏も、そうした音楽のひとつである。CD「言葉を用いない詩」では、様々な民族音楽の発声をベースに、新しい表現を試みている。しかし、声の演奏を好んで行う一方で、作曲家としての私には、声のための作品(楽譜に書かれたもの)が少ない。
理由のひとつは、記譜の問題である。
様々な民族音楽から影響を受けた声の音楽は、五線譜への記譜に向かない。五線譜は、音の長さと高さを表すには適しているが、声の音楽において重要な「音色」や「抑揚」を表すことが難しいのである。
そもそも、五線を用いて音楽を記録するという文化は、世界全体から見れば、ごく限られた地域、限られた時代のものでしかない。ある種の民謡においては、音の高さや長ささえも一定ではなく、そうした歌を五線譜に採譜しようとすれば、歌うたびに違う結果に悩まされることだろう。
イタリア古典歌曲のように五線に記譜された音楽であっても、音色や抑揚を明確に記すことは不可能と言って良い。声楽家達は、音色や抑揚を、その音楽の様式に応じた「伝統的慣習」として、楽譜からではなく先達から受け継ぐ。
したがって、特定の伝統的慣習に拠らない音色や抑揚の伝達のためには、何らかの特別な手段が必要となる。器楽では、そうした音色が求められる時、楽器の部位を言葉や図で示し、「○○を手のひらでこする」というような方法で、奏法を説明することが多い。だが、声の場合は、喉が目に見えない場所にあるため、そういった説明は極めて難しい。20世紀、様々な楽器において奏法や音色が新しく開拓され拡大されていったが、実のところ、声の音楽の場合は、音色や奏法が比較的拡張されなかった。それは、新しい奏法を声楽家達が共有できるように説明することが、極めて困難だからである。
それでも、L. ベリオやG. シェルシなど作曲家は、声のための興味深い作品を残している。だが、彼らの音楽は楽譜に書かれてはいるものの、大抵は特定の演奏家のために作曲されている。そうした作品を別の声楽家が歌う場合、初演時の録音を聴く事なしには、なかなか作曲家の意図に沿って歌うことはできない。こうした現象からも、声の音楽を楽譜にすることの限界を窺うことが出来る。
20世紀、他の楽器に比べ、声の音色があまり拡張されなかったことはすでに述べたが、それは記譜の難しさによるものだけでなく、様々な発声の開拓に多くの声楽家達が消極的だったことも、要因のひとつではないだろうか。 経験から学んだことだが、多くの声楽家は、作曲家から特殊な発声を要求されることを良しとしない。馴染まない発声で演奏することは、喉に傷害を負う危険性があるからというのが理由のひとつである。
確かに、器楽作品においても、楽器を傷める可能性のある奏法に対して消極的な演奏家は多い。ましてや、声は楽器と違って替えのきかないものであるがゆえに、その恐怖は大きいものだろう。
他にも、「馴染まない発声では、充分な音楽表現ができない。」、「発声について悪い癖がついてしまう。」、「生理的にそのような声は出したくない。」など、様々な理由がある。
しかし、器楽においてもそうだが、新しい奏法は、しばしば演奏家と作曲家との共同作業によって開拓されてきた。前述のL.
ベリオやG. シェルシらの作品に見られる様々な表現方法もまた、声楽家との共同作業によって生まれたものだ。 新しい音色の開拓のためには、様々な発声についての理解が必要なのは言うまでもないが、それにも増して必要なのは、新しい音楽に対する欲求そのものである。L.
ベリオの声の作品に大きく関与したK. バーベリアンは、様々な音色を操り、多彩な様式の音楽に通じた卓越した声楽家であったが、彼女の歌う半ば即興的な作品「ストリプソディ」を聴けば、いかに彼女が様々な音色を表現することを喜んでいるかを感じることができるだろう。だが、そうした積極的な声楽家は、残念ながら稀である。
声楽家に対しやや批判的なことを書いたが、実際、私は声楽家達に、より積極的になって欲しいと願っている。声の音色には限りない可能性があり、それらを開いていくことは、声楽家達にとって大きな喜びとなるはずだ(もちろん自らの喉をいたわることは、最も大切である。)。
ところで、20世紀の声の音楽を見渡した時、音色を重視した音楽について興味深い仕事をしている音楽家は、作曲家や声楽家よりも、むしろ即興演奏家達に多い。楽譜を必要とせず、自己の責任においてかなり大胆な発声の実験が可能な彼らは、これまで述べた問題から解放された存在である。その強みは計り知れない。
私もまた、楽譜を用いずに自ら演奏することによって、これらの問題を回避することができた(ここでの「回避」は、消極的な意味ではなく、適切性を見出すための積極的な「回避」である。)。「言葉を用いない詩」には、その成果が収録されている。だが、私が五線を用いて声楽家のために作曲をする時には、再び同じ問題が立ちはだかるだろう。その時は、また新たな回避の方法を考えなくてはならない。
これは、私だけの問題ではなく、音色を重視した声の音楽を作ろうとする全ての作曲家に共通した問題でもある。私は、多くの作曲家達(私自身も含め)が、これらの問題にどう対処していくかに大変興味がある。それらは、今後の声の音楽の変遷の大きな鍵となると思えるからだ。
初出:2004年11月 音場舎通信67号