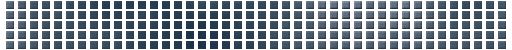
「椿姫」は,アレクンサンドル・デュマ・フィス(1824-1895)による原作のタイトル。オペラ版のタイトルは「ラ・トラヴィアータ(道を踏み外した女)」だが,日本では原作のタイトル「椿姫」が用いられることも多い。
「椿姫」は,デュマ・フィス自身の実体験が元となった小説で,高級娼婦マリー・デュプレシスとの恋愛が描かれている(オペラでは「ヴィオレッタ」という名前で登場する。)。
ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)は,19世紀のイタリアオペラを代表する作曲家のひとり。「耳に残るメロディ」「声を聴かせるためのオーケストレーション」という彼の音楽的特徴は,歌を重んじるイタリアオペラの伝統を受け継いでいる。
原作の小説「椿姫」の発表は1848年,ヴェルディ作曲のオペラ初演は1853年であった。物語の舞台も時期をほぼ同じくしており,19世紀半ばのパリの社交界が舞台となっている。
第1幕:ヴィオレッタのサロン
前奏曲の冒頭が美しい。透明な弦楽器の音色が,神経質なまでの緊張感を伴って空間に放たれる。短いが,作品中最も美しい音楽のひとつである。息を殺して耳を澄まそう。
宗教的な印象さえ感じさせる冒頭に続き,音楽は一転する。のどかな旋律を経て,ヴィオレッタのサロンへの幕が開く。軽やかな音楽に乗って交わされる台詞が,耳に心地良い。
ヴィオレッタはパリの高級娼婦である。当時の高級娼婦は,パトロンに生活の全てを保護されていただけでなく,公的な場所にも同伴され,その美貌や才知が社交界で競われたという。成功すれば巨万の富を得られる一方,いつパトロンに捨てられるかも知れない,不安定で厳しい世界でもあった。彼女にとっては,愛でさえ,お金で取引される商売道具のひとつに過ぎなかったのである。
一方アルフレードは,地位も金もない一青年である。彼の歌う「乾杯の歌」は,高級娼婦とパトロン達が集うこの場にふさわしく,快楽を賛美した内容である。しかし,実のところ,彼は場の雰囲気に合わせて少々無理をしている。決して金持ちではないアルフレードは,彼らの知る快楽を味わったことなどなかったのだから。
二人きりになったアルフレードは,ヴィオレッタに思いの丈を打ち明ける。無一文でヴィオレッタに愛の告白をするアルフレードの行動は,ここでは明らかに場違いである。彼がいかに真剣であろうと,社交界の厳しい現実を生きてきた彼女にとって,アルフレードは「分不相応なガキ」でしかなかっただろう。真剣なアルフレードに対し,ヴィオレッタはアルフレードを軽くあしらう。気まぐれなフルートがヴィオレッタのあしらいを強調する。しかし,この場面,二人の気持ちが噛み合っていないにも関わらず,音楽はすぐにふたりを一致させるのだ。歌の最後,二人が作り出すハーモニーが実に美しい。台詞や態度とは裏腹に,アルフレードに惹かれていくヴィオレッタの心情を,音楽が暗示しているかのようである。
客達が戻り,再び宴会の場面が始まる。早口で囁くような歌が,弦楽器とともに聴き手の耳をくすぐりながら,小気味良い音楽とともに次第に盛り上がり,華やかな宴会を演出する。こういった場面における音楽の盛り上げ方は,ヴェルディの最も得意とするもののひとつであろう。
続くヴィオレッタひとりの場面,彼女はアルフレードの言葉を噛み締め,自問する。抑制されたオーケストラが,宴会の後の寂しさを強調する。ここでは,アルフレードの純愛に揺らぐ気持ちと,これまで通りの快楽に生きようとする気持ちとの葛藤が表現されている。彼女の心そのままに変化する音楽とともに,ヴィオレッタの多彩な声を心行くまで味わおう。
彼女の心にアルフレードが深く入り込んだのは,彼の純粋さが彼女にとって新鮮だったからに他ならない。アルフレードは愛をお金で買おうとはしなかった。彼の場違いな行動こそが,ふたりの想いを近づけたのである
第2幕−第1場:パリ郊外の別荘
まず,アルフレードひとりの場面。彼は,ヴィオレッタとの新生活の喜びを歌うが,その後生活費の実態を知り,驚く。つまり,彼はそれまでヴィオレッタと同棲していながら,生活費の出所を知らなかったのだ。この場面からは,彼の世間知らずな一面が窺える。ところで,本作品におけるアルフレードは,一貫して単純で直情的である。だが,彼が真っ直ぐな性格であるがゆえに,ヴィオレッタの数々の苦悩が,よりはっきりと照らし出されている。
続いて,ヴィオレッタとアルフレードの父親 ジェルモンが登場し,ふたりのやりとりが描かれる。ここで最も興味深いのは,ヴィオレッタの「過去」と「神様との関係」である。ふたりのやりとりには,しばしば「神様」という言葉が登場する。彼女の「彼を愛し,悔い改めた私のために,神様は過去を消してくださいました。」という台詞からは,彼女のこだわりを窺い知ることができる。アルフレードのために全財産を投げ打つという行為も,彼への愛のためだけではなく,高級娼婦であった過去に対する彼女自身の自責の念が関係しているのではないだろうか。そしてジェルモンも,そうした彼女の心情を察していたに違いない。彼は「天の意思によって祝福されなかった絆」「こうした言葉を言わせ給うのは神様です。」と,彼女の心に最も効果的に突き刺さる言葉を選んでいる。
ヴィオレッタに非情な請願をするジェルモンもまた,興味深い人物である。この場面,ジェルモンはヴィオレッタに引けをとらない存在感を持っている。彼は世間体のために2人の愛を引き裂こうとする。ともすると単純な悪役になりがちな役回りを演じているにも関わらず,どこか悲しみを帯びた人物として映る。ここで彼は,すべてを理解したのだ。アルフレードのために全てを投げ打ったヴィオレッタの決心も,彼自身の残酷さもすべて理解した上で,世間体を重んじた。彼は家族を愛し,その幸せのためには,「世間体」がいかに重要かということを良く知っていたのである。彼もまた,苦悩している。
続く場面,別れの手紙を書くヴィオレッタの心情を代弁するかのようなクラリネットが,悲痛に歌う。短い場面だが,ここにもヴェルディの卓越した「うたごころ」を見ることができる(同様に,第3幕における手紙の朗読の場面でのヴァイオリンの旋律も印象的である。)。
総じて,この第2幕第1場,心理描写に重きがおかれている。ヴェルディは,そうした場面において,過剰な音楽で雰囲気を盛り上げたりはしなかった。音楽は物語のために「適切な分」しか用意されていない。歌手にとっては,その力量が最も問われる部分でもあるだろう。聴衆もまた,登場人物の心情を感じ取り,味わいながら聴くことが要求される。ただ漠然と聴いているだけでは,本作品中,最も退屈な場面になりかねない。
第2幕−第2場:ヴィオレッタの友人宅の大広間
第1場とはうって変わって,音楽は華やかな雰囲気を演出する。夜会の臨場感がよく表現されており,間に挿入される「ジプシーの歌」は,心理的描写に偏りがちな本作品中,音楽的にも場面的にも絶妙なアクセントとなっている。表面と内面,その両方を演出する音楽からは,ヴェルディの表現力の深さが窺える。
この場面の最後,ヴィオレッタ,アルフレード,ジェルモン,そして宴会の参加者達が歌う重唱は,見事である。それぞれが自らの心の内を歌うこの重唱では,さまざまな感情が交錯し,ひとつの大きな渦となって聴き手を圧倒する。
第3幕:パリ下町のヴィオレッタの部屋
弦楽器の響きで幕が開く。これは前奏曲の冒頭で奏でられた,あの美しい音楽である。透明感のある響きは,輪郭を次第にはっきりさせる。悲しげな旋律は,ヴィオレッタの孤独を表わすのだろうか。
ヴィオレッタは,死に瀕している。彼女は病の床で,自らの死を強く意識し,神様に語りかける。果たして彼女は,どこで道を踏み外したのか。歌は多くを語らない。我々に再考を促すだけだ。
ところで,ヴィオレッタを演じる歌手には,極めて多様な表現が要求される。高級娼婦としての洗練された華麗さと,その内面に秘められた純真さ,愛に生きようとする強さ,神様への厚い信仰心,死に瀕し自らの人生を回想する心情など。これらを一人で演じ歌いきることは,技術的にも表現的にも困難を極める。だが,彼女が実に様々な面を併せ持っているがゆえに,聴き手の心にも様々なヴィオレッタ像が映し出されるであろう。
多面的なヴィオレッタに対し,アルフレードとジェルモンは最後までひとつの性格を貫き通す。彼らが現れる場面では,アルフレードは相変わらず「パリを離れて一緒に暮らそう」と明るい未来を夢見ており(だが,死に瀕した彼女にとって天真爛漫な彼の言葉はどれほど救いになっただろうか。),ジェルモンは後悔の念を歌う。ここで興味深いのは,彼らの歌う心情が,それぞれ孤立している点だ。3人の心情が微妙に噛み合っていない空間には,悲しさだけではなく,何とも言えない虚しさも同居している。
音楽は空間に漂い,物語を終焉に導いていくだろう。幕が降りたその時,聴き手の心はどんな色に染まっているだろうか。
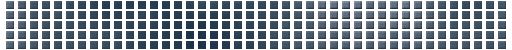
本公演では、解説だけでなく、チラシの文章も書きました。
彼女には、未来がなかった。
あるのは、愛に溢れる、今、だけ。
だが、どんなに深い愛の中にあっても、
過去を無くしてしまうことは、できない。
愛すること、去ること。そして沈黙。
与えられた、僅かな時間、
ただ、ひたむきな愛だけが、
彼女を衝き動かしてゆく。
La Traviata 道を踏み外した女。
この、かなしい椿姫を、誰がそう呼ぶのだろう。
愛に酔おう。
聖なる愛に―――孤独な愛に。