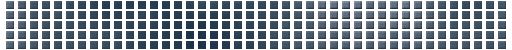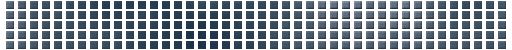
うみのうた
ことば 梶田明子 & 寺内大輔
今、私たちは波止場に立つ。
旅に出ようと誘われているのだ。
水先案内人は山岸靖という人。
私たちに背中を向けたまま、彼は海を見つめている。
船に乗り込むも乗り込まないも、あなた方一人一人の勝手だと、
その背中は無言のままに私たちを突き放す。
寺内が大学2年生の頃だ。
副科声楽のレッスン中、山岸靖先生は言った。
「音楽はこれから先、どっちへ行っちゃうんだろうな。」
音楽家を志し、修行中の私にとって、
それはきわめて重要な問いかけだった。
私達は、少しの間 会話を交わしたが、
結局、この問いに対する答えは、私にも先生にもわからなかった。
ただ、確かなことは、
音楽がどこへ行くのかわからなくても、
音楽家は、自らの音楽の行き先を決めなくてはならないということだ。
今夜の演奏会が、ひとつの旅だとすれば、
そこには、山岸靖が辿り着いた場所が見えるだろうか。
あるいはもしかしたら、
彼は今もさまよい続け、そのことを楽しんでいるかも知れない。
第一部 歌曲
I イタリア歌曲
P. チマーラ作曲「海の詩」
海が好きなのだそうだ。
どんなふうに海が好きなのかは、
この曲を山岸がどんなふうに歌っているかを聴けば、わかる。
たぶん、夜の海。
穏やかな波。
(しかし、いつ激しさへと変わるか予測のつかない力を秘め。)
月の光。
まるでビロードで包まれた手のように、海のおもてをなでる。
遮るもののない視界。
ひろがり。
永遠の、ひろがり。
永遠の、受容。
(彼とともに海の旅に出るかどうかは、もう少し彼を知ってから。)
「ストルネッロ」
(ストルネッロは民謡の一つ。詩のかたち。)
海の匂いのする恋のうた。
恋人は、長い髪に汐の匂いを漂わせた
赤い唇の美しきニンフ。
男の情熱的な誘いの言葉に
両腕を広げて微笑む。
「春は再び!」
そういう男なんだ、この人は。
何の憂いもなく思惑もなく恋に堕ちる。
何も考えない。
美しいものを美しく感じたいだけ。
だからわからない、
女の苦悩も不安も。
苦悩する女を前に、この人は戸惑う。
私にはこの人の、
悲しみではなく
戸惑いが聞こえる。
(「髪結いの亭主」ていう映画があったよね。あの亭主みたい)
「海辺の光景」
再び私たちは船に乗る。
これが私たちの水先案内人が用意した海。
海と空の境に目を向けた彼の背中。
私たちは今、
彼と共に船出する。
II 日本歌曲
(ここが、私たちの旅の、最初の停留地。
なぜ彼はここを選んだのだろう。
・・・・私の思いは、まずそこにとどまる。
よりによって、こんなしんしんとした曲ばかりを。
異国の言葉で高らかに恋を歌う人の、
深い深い深い底には、こんな音たち、こんな言葉たち、
こんな色たちが沈み込んでいると、
それを私たちに見せたかったのか。)
溝上日出夫作曲「落葉のように」
ムードを味わおう。
旋律と伴奏が醸し出す、切ない表情。
それは、聴き手ひとりひとりのもつ思い出を喚び起こすに じゅうぶんだ。
歌とともに立ち現れる言葉もまた、
大気中に、ひとつひとつ、
あたらしい色を、加えてゆく。
溝上日出夫作曲「雨の言葉」
「わたしがすこし冷えてゐるのは」
に始まり、すべてが一人称で歌われる、
極めて閉じた世界。
歌い手は、自分自身と極限まで向き合わなければ、
この歌を歌うことはできない。
林光作曲「四つの夕暮れの歌」
I「夕暮れは大きな書物だ」
夢だろうか。
しかし、僅かに手触りが感じられる。
夕暮れの歌、昼夜の境目にあたる時間帯。
不安定な響きの組み合わせは、
夢と現実の狭間の、軽い混乱に導いてゆく。
II「誰があかりを消すのだろう」
谷川俊太郎の言葉には、力がある。
「お父さん」、「かぜ」、「あかり」……
特別な単語はひとつもないが、
その組み合わせは、ユーモアと不気味さを、
絶妙なバランスで同居させている。
旋律には跳躍が少ない。
ほとんどが近くの音へ動いている。
だが、その僅かな動きは、
耳で追う聴き手を、
一瞬で別の世界へと導くだろう。
III「誰もいない隣の部屋で」
語るように歌うことによって、
世界を現実的なものにしている。
歌からは、鮮明な映像が喚び起こされる。
かげがちらっとめをかすめる
だがわたしがおうともうだれもいず
あたりまえなゆうがたになる
わたしは、どこにいるわたしなのか。
昼夜の境目の時間帯というよりも、
昼と夜とが同時に存在している世界なのではないだろうか。
IV「死者をむかえる夜」
はっきりしたビートがある。
明るい葬送行進曲、とでも言えば良いのだろうか。
少なくともこの歌では、
「夜」と「死」は明るいものらしい。
ピアノは、ばらばらになりそうな響きを
危なげに連ねながらも、
規則正しいリズムを繰り返してすすむ。
第二部 プッチーニ作曲
オペラ「トスカ」より
(次の停留地。ここは終点だろうか。
それとも、
これより先の行く先があるのだろうか。
ここで山岸は、客席へと誘い、
自らは舞台へと上がる。
幕が開いた。)
舞台は恐怖政治が行われていた1800年のローマ。画家カヴァラドッシが教会で聖母マリア像を描いているところに、政治犯のアンジェロッティがやってくる。
脱獄したアンジェロッティを助ける算段をしているところにトスカがカヴァラドッシをたずねてやってくる。
嫉妬深いトスカはカヴァラドッシが女性と話していたと思い込みなじるが、やがて、カヴァラドッシの愛を再確認して教会を去る。
「愛の二重唱」
寺内:「愛の二重唱」―――なのだけど、ふたりの歌が重なる箇所は、ほんの一瞬だけなんですね。
そこに行くまでは、ふたりは交互に歌ったり、メロディをつないだりしながら、お互いの感情をじわじわと高揚させていくわけだけど、これって、実は「じらしテクニック」なのかもしれない。誤解を恐れずに言えば、なんだかエロティック。
ふたりの対話が、そのまま聴き手に対するじらしに繋がっているような気がする。
梶田:プッチーニって、女をよく知ってる。
「よく知ってる」というと、語弊があるかなぁ。女ってこうだよね、というところと、女って男にこうしてほしいんだよね、というところの両方を知っている、ていう感じ。
女って、好きな人の前では雄弁なのよ。黙って見つめてるときだって、心の中では言葉がいっぱい。
「この人の目、何が写っているのかしら。」
「私のどこが好き?」
「あ、いま、他の人を見た?」なんてね。
カヴァラドッシとトスカの会話は、いつもトスカが先導。
「今誰と話してたの?」「この女は誰?」。
雄弁で嫉妬深いトスカの言葉を、カヴァラドッシは悠々と(した旋律で)受け止める。
「僕のやきもち焼きやさん!」
トスカは、わざと(でも心のそこでは直感的に不安を感じてるのよね)疑いの言葉を投げかけながら、その子供っぽさを受け止めてもらうことで、彼の愛情を確かめる。
これがね、カヴァラドッシが直情型でしかも短気な男で
「なんだとぉ!そんな繰言なんかに付き合ってられるか、めんどくせぇ」
なんていったとすると、興醒めなのよ。
この不安と甘さの入り混じった、言葉の戯れ、これこそ女にとって恋の醍醐味。
寺内:「女にとって恋の醍醐味」、なるほど。
怖いなあ、確かに「めんどくせえ」なんて口が裂けても言えんね。
「女にとって恋の醍醐味」というのも確かにわかるんだけど、「めんどくせえ」っていうのも、正直その通りなんだよな〜。
そう感じる僕は、「女を知らない」ってことになるのかな。
でもね、同性から見た場合でも、こういう女性のことを「めんどくせえ」って感じる人、多いんじゃないかな。
女性の皆さん、どうですか?
梶田:友だちだとしたら面倒くさい、たしかに。
だけど、大概の女が、多かれ少なかれ、こんなことをやったことがある。
たとえ心の中でだけだって、こんな問いかけを男にしたことがある。
ねぇ、女性の皆さん。
だって、女って言葉のほうが感じるときあるもの。
寺内:うーん、「言葉で感じちゃう」っていうのもあるんだけどねえ。
男にとっては、それは途中に過ぎないわけだから、じらしたからには、もっと直接的な方法で責任を果たして欲しいって思うんですよ。
「歌に生き、恋に生き」
カヴァラドッシは警視総監スカルピオに捕えられ、拷問にかけられている。スカルピオは、カヴァラドッシを救いたければ、自分に身を任せろとトスカに迫る。
嘆き悲しむトスカは、「歌に生き、恋に生きてきただけなのに、なぜこのような目にあうのですか」と神に訴える。
寺内:「声を聴かせる歌」ですね。
旋律も、伴奏も、音楽の表情の変化も、すべては、声を生かすためにあるような気がするんです。
本当に美しい。
梶田:そう、美しいよね、この旋律。
歌詞の頭も印象的。 "Visi d'arte, visi d'amore"(歌に生き、恋に生き)だもの。
トスカって可愛い。
絶世の美人歌手のはずなのに、どこかで自信がなくて恋人に他に女がいるんじゃないかって疑ってみる。
気が強そうにみえて、その実、まるで小さな女の子。
男たちの様々な思惑の中で、彼女だけが、その場その場の感情で生きているのよね。
愛しさや、恐ろしさや、心細さ、そして盲目的な敬虔さ、、、。
それを女の愚かさ、というのなら、その通り。
でもプッチーニはきっと、この女の愚かさこそが、女の魅力だと思ってる。
この、ソプラノならではの透明感を十分に引き出す旋律。
「今」だけを心のままに生きる女の愚かさ。
だから悲しくて、どこまでも美しい。
寺内:確かに可愛い。
でも、もうひとつ付け加えたい。
それは、「絶世の美人歌手のはずなのに」っていうギャップ。
こういうギャップって、すごく魅力の要素になったりするでしょ。
「彼って、怖そうなのに優しいの!」とかね。
プッチーニは、そういうギャップが醸し出す魅力についても意識していたんじゃないかなあ。
梶田:絶世の美女だから、嫉妬深い、っていうのもあるよ。
美しさの利点を知っているだけに、さらに美しい女がいたら、、と不安になる。
人間のコンプレックスってきりがないよね。
そう考えてみれば、プッチーニが知っていたのは女だけじゃなくて、人間の業ってことかな。
「星も光ぬ」
処刑を前にしてカヴァラドッシは、わが身を嘆く。そこに、トスカが現れる。トスカはスカルピオを殺したこと、その前に、カヴァラドッシを助けるという約束をさせたことを話し、「これで私たちは自由の身よ!」と喜ぶ。
寺内:「ピアノと歌との二重唱」と言っても良いかもしれませんね。ピアノもよく歌っている。
本当にきれい。
しかし、その後が長くないですか?
ふたりが将来の計画について話し合う場面なのだけど、やたら長々と話し続けている。
絶望から希望への喜びを実感するためには、ある程度の時間が必要なのかもしれないけれど。
梶田:この「トスカ」ってオペラ、プッチーニにしては珍しく(?)、ストーリーの運びや、それに伴う心理描写のほうを重視したんじゃないかな。
トスカがカヴァラドッシのもとへとやってくるところも、人を殺した興奮と不安と、これで恋人を救えるという喜びの複雑さが、よくわかる。
そのあと、恋人を目の当たりにして、ようやく落ち着くことができて、二人で将来のことを話し合う。
舟歌風のオーケストラにあわせて、二人が船出していく光景が、聴く側にも見えてくる。
そしてラスト。
煌々とした光の中で二人の声が完全に一つになる。
私には、ここではもう、神の懐に抱かれた完全なる歓喜にすら聞こえるのよね。
。。。。。。で、ここで今日はおしまい。
ほんとうの「トスカ」はまだ落ちがつくんだけど。
今日はここで、おしまい。
だって、山岸先生の、門出だものね、今日は。
(というわけで、お話の続き、トスカとカヴァラドッシがこの後どうなったかをお知りになりたい方は、どうぞCDか舞台でお楽しみください)